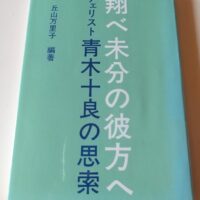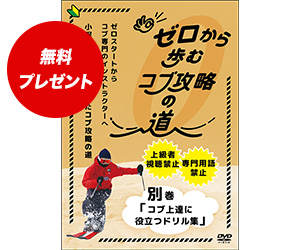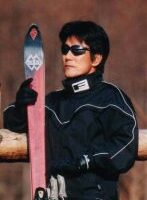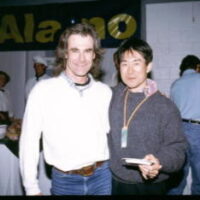スキー教師のジレンマ

スキー教師として、わたしにはジレンマがあります。たぶん同じジレンマを、多くのインストラクターが抱えているのではないか・・・・とも感じているので、それについて書いてみます。
まずスキー教師が指導において多くの時間を掛ける内容に、制動技術(ブレーキ)があります。いかにしてスピードを落とし、滑走スピードをコントロールするかに多くの時間を費やします。安全性を考えたら、とうぜんのことです。
わたしのレッスンをご受講になるスキーヤーの多くは、コブでの滑りを求めていらっしゃるので、コブ斜面でのブレーキ技術に多くの時間が割かれることになります。
コブ斜面では、整地と性格が逆になる場合も多いのです。たとえば整地ですと、スピードが上がれば上がるほど、スキーはズレやすくなります。ですから、高速ターンのスピードコントロールはごく自然にスライドへと繋ぐことができます。また整地においては、より上級者になると、ズレやすくなる環境下でズラさないというテクニックを学ぶことになります。
しかしコブでは滑るラインにもよりますが、多くの場合、スピードが出るとスキーはズレ難くなるのです。たとえばバンクターンの場合、スピードが出れば遠心力でスキーがバンクに押しつけられ、ズラすことが難しくなります。ダイレクトラインを狙うなら深い溝と壁に阻まれ、ズラす場所すら見あたりません。こうしたズラし難い環境下で、どのように摩擦抵抗を生みだしてスピードコントロールするのかということに時間が費やされることになります。
ズレやすい環境でのズレ(もしくはキレ)を可能にする整地でのテクニックと、ズレ辛い環境で摩擦抵抗を生むためのコブテクニックは、自然と異なったものになります。
現在のスキー技術は、アルペン競技のトップスキーヤーの技術が目標にされています。そのため日本の基礎スキーでは回転弧の大きさもスラロームで使われる一般的な回転弧が「小回り」とされ、一昔前のショートターンよりずいぶん大きくなっています。

そんなアルペン競技ではタイムが正義です。
陸上競技や水泳競技のように、どんなフォームで走ろうが泳ごうが、早い者が勝利する世界です。価値判断にタイム以外はなく、たとえ転んだりタッチダウンしても、早ければ勝ちです。
こうしたタイムが絶対の競技に真剣に取り組む方は、とうぜんトップ選手たちの技術を真似ることになります。
モーグルやスロープスタイルは審判スポーツなので、こうした絶対性はアルペン競技ほど存在していません。わたし個人は選手としてコーチとして、モーグル競技で大きく三回の技術変化を見てきました。そしてそこで学んだことは「技術に絶対はない」ということです。
タイム絶対の世界を審判スポーツのなかに持ち込むこと自体、無理があるように感じています。もっと言えば、「基礎スキー」というのはそもそも競技として成り立つのでしょうか?
スキーにおいて、世界最高峰のアルペンスキー技術を、基礎スキーに持ち込むのが良いのか?
そこにジレンマがあります。極端な言い方をすれば、F1レーサーが大切にしている技術を、一般道に持ち込むようなものですから。またトップアルペンスキーヤーの技術は、あの高性能な身体能力あってこそ可能になる部分も多いと考えられるからです。
「スキーは物理学」だと、わたしは考えています。ですからアルペン競技と一般スキーの間の共通点もたくさん見えます。しかしスキー指導という観点から見ると、百分の一秒を争う競技技術を「基礎スキー」と呼ばれる分野に持ち込むことにはマイナスもあると信じられます。
いくつかの言い方ができますが、強靱なブレーキなしに加速ばかり教えるのは無謀です。
カーヴィング技術は素晴らしいものですが、それに固執することも危険です。
スキー技術においては、求められるターン弧と求められるスピードで、選択肢がたくさん生まれます。その技術の選択肢は「スキーヤーが求める方向性」によって最適の「解」が変わることも事実です。
たくさんの異なった状況下でバックカントリーを滑ってみると、いかにシュテム操作や抜重操作が安全性を増し、より快適な滑走をもたらすかに気付きます。

わたしは「内向・内傾」のスキーに反対してきました。これは今でも同じですが、「スキーヤーが求める方向性」 によっては内向・内傾技術も大いに役に立つと考えています。わたしが反対したのは「内向・内傾」のスキーをスキーの基本に置くべきではないということであって、応用技術としては素晴らしいものです。
技術の基本を物理学的側面から見る時、内足より外足への荷重が合理的ですし、「外向傾」と呼ばれるいわゆる「くの字姿勢」が適しています。スキーの物理学で重要になる「迎え角」を作り出すためにも、やはり「外足荷重」と「くの字姿勢」が最適となります。そのためにプルークファーレンやプルークボーゲン(ウェッジターン)の練習がとても大切になります。しかし、いったん基本的な動作を身につけたなら、自分の目指す方向にいろいろ応用技術や工夫を重ねて行くべきとも考えています。
販売されているスキーを見ると、スキーそのものが細かく分化して、ニッチな方向性を示しています。最新のGSスキーとパウダー用ファットスキーは、とても異なっていますし、SLスキーとツインチップスキーも大きく性格が異なっています。
どんなに優れたスキーヤーでもファットスキーでスラローム競技に勝ったり、モーグル競技で良い成績を得ることは不可能でしょう。反対にモーグルスキーで深いパウダーを滑ることも難しいです。
ですから、まずはスキーヤー自身がどんな方向に行きたいかを考え、それに適した用具を使い、方向を理解してくれる指導者と出会うことが、上達の近道となるのではないでしょうか。
基礎スキーヤーの中には、非常に細かい技術に固執される方が見受けられます。
細かいところを大事にされることは大切ですが、スキー技術は状況の変化や使用する用具の変化で、最適な「解」が変わることも事実です。求める方向によって答えが変わるのですから。
どちらにしても、スキー教師として、わたしはこんなジレンマを持ちながらレッスンをおこなっています。
余談ですが、スキー技術について書くと、時折たいへん攻撃的なご連絡をいただくことがあります。そんな気持ちを持たれたみなさま、このブログがあくまで「独り言」というタイトルであることを、思い出されてください。
もうひとつ余談。
来シーズン、ついに英語でスキー技術書を発表することになりました。とてもワクワクしています!
https://ameblo.jp/tonakai-no-hitorigoto/entry-12920877505.html